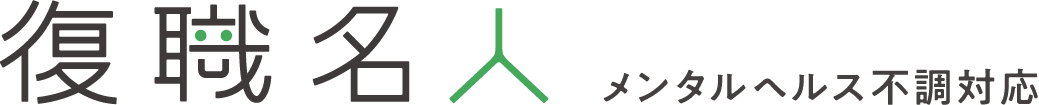職場のメンタルヘルス対応において、「どう対応していいかわからない」「対応が長引いて現場が疲弊している」といったお悩みはありませんか? その混乱の多くは、実は「医療的健康管理」と「業務的健康管理」という2つの異なるアプローチを混同してしまっていることに原因があります。
この2つを明確に区別し、場面に応じて使い分けることが、難渋事例を生まないための第一歩です。今回は、その重要なポイントについて解説します。
*本記事は「復職名人が読む三手先」第1回の内容をもとに構成しました。
医療的健康管理と業務的健康管理の定義
「2つの健康管理」の定義は次の通りです。
医療的健康管理
病院での医療をモデルにした健康管理です。目的は「個人の健康増進」にあり、個人の希望を最大限に尊重します。これは福利厚生的な位置づけであり、企業にとって必ずしも義務ではありません。
業務的健康管理
労働契約と労務管理に基づく健康管理です。目的は「就業に支障のない労働力の確保(全体最適)」です。これは安全配慮義務の履行を含むため、企業の義務であり、必要であれば業務命令を伴うこともあります。
最大の違いは、「誰のために行うか」です。医療的健康管理は「個人のため」に行いますが、業務的健康管理は「組織のため(および組織の一員としての労働者のため)」に行うものです。
なぜこの区別が必要なのか
多くの産業医の育成過程は、50単位の基礎研修会を受講して単位を取得して、日医の認定産業医となります。この過程で、体系的な産業医学について学ぶ機会が必ずしもあるとはいえず(50単位をバラバラで取得することもあるため)、残念ながら、正規なフォーマルトレーニングを受けないまま実務に就きます。加えて、産業医にはOJTが基本的にはありません。
その結果、病院で学んだ医療知識をベースに、職場での健康管理を「ダウングレードされた医療」として実践してしまう傾向があります。これが医療的健康管理に偏る理由です。
臨床現場での「患者第一」の思考(医療的健康管理)をそのまま職場に持ち込むと、結果的に、「本人が辛いと言っているから配慮してあげたい」「異動させてあげたい」といった、労働契約や就業規則を飛び越えた個別対応が提案されてしまうことがあります。
しかし、職場はあくまで「働く場所」であり、治療の場ではありません。労働契約に基づき、集団としての公平性を保ちながら運営される組織において、個人の事情のみを優先する医療的アプローチを続けてしまうと、現場は混乱してしまいます。
一方、業務的健康管理は、労働契約や就業規則といった文書に基づいているため、担当者が変わっても同じルールを一貫して適用できます。この点で、医療的健康管理の「職人芸的」な特性とは大きく異なります。
業務的健康管理は、ルールと契約に基づき、誰が担当しても同じ結論に至る「再現性」と「公平性」を保つために不可欠な視点なのです。
医療的健康管理がもたらす悪循環
医療的健康管理に偏った対応を続けると、次のような悪循環に陥るリスクがあります。
- 過剰な配慮の常態化: 「本人の希望」を優先しすぎた結果、本来必要な業務を免除したり、根拠のない異動を行ったりしてしまいます。
- 周囲の疲弊: 特定の個人のために業務を肩代わりさせられた同僚に不満が蓄積し、組織全体のモチベーションや生産性が低下します。
- 問題の長期化: 「配慮」という名のもとに、問題の本質(労務提供ができていない事実)が先送りされ、復職と再休職を繰り返すような長期的な難渋事例となってしまいます。
さらに問題なのは、会社側も人事も産業医の医療的判断に頼り切ってしまい、自らが業務的な判断をする責任を放棄しがちになることです。
関係者による役割分担
業務的健康管理では、人事・上司・経営層が主体的に関わります。一方で、医療的健康管理において主体となっていた(丸投げさせられていた)産業医・保健師などの産業保健職は、その職務を支援する立場に回ります。
• 人事・総務: 業務的健康管理の主体です。就業規則や労働契約に基づき、労務提供が可能か否か(=働けるか休むか)を判断します。
• 上司: 部下の「業務遂行状況」を管理します。顔色を見て病気を探すのではなく、納期遅れやミスといった「事実」を報告する役割を担います。
• 産業医・保健師: 医学的見地から、会社が提示した労働条件での就業について「ドクターストップ(医学的な不可)」があるかどうかのみを判定します。労働条件の決定そのものには介入しません。
医師に「働けるか」を聞いてはいけません
よくある間違いとして、主治医や産業医に「この人は働けますか?」「どのような配慮が必要ですか?」と丸投げしてしまうケースがあります。 医師は職場の詳細な状況を知らず、労働契約の内容も把握していないことがほとんどです。そのため、医師の回答は「本人の希望(=楽な部署に行きたい、残業したくない)」を代弁したものにならざるを得ません。
会社が聞くべきなのは、「会社が定めた条件(原職復帰・フルタイム勤務など)で就業させた場合、医学的に見て悪化のリスクが著しく高いか(ドクターストップか)」のイエス・ノーのみです。就業の可否を決定する権限は、医師ではなく会社(人事)にあることを忘れないようにしましょう。
いきなり面談の問題
産業医実務の場面では、何の情報もなく「いきなりの面談」が設定されることが少なくありません。
背景には、医療職が「初診患者の対応」に慣れているため、事前情報なしでもやれるという思い込みがあるのでしょう。
一方、ビジネス的思考では、判断には情報が不可欠です。前提情報もなくいきなり打ち合わせを設定するようなことはありません。
こうした場面に関わらず、両者のアプローチには大きな違いがあります。
親代わりの健康管理
労働安全衛生法は、事業者が親として、子である労働者の健康管理をしてあげることが前提になっています。具体的には、健康診断を実施する義務が事業者に課せられ(労働者にも課せられていることには驚きです)、事業者は労働者の許可なく結果を確認し、必要な措置を労働者の意見も聞かずに取ることが、法律上は求められています。まるで親代わりの健康管理です。
また日本の雇用制度には、「家族手当」など労務提供の対価ではない給与が存在し、いわば企業が「親」的役割を果たすことが前提とされています。
この背景があるため、企業も労働者も、企業が労働者の「健康」まで面倒を見るべきだという感覚に陥りやすいのです。
しかしながら本来は、労働者が自身の健康管理を自律的に行う、ということが求められるはずです(特に現代においては)。そうした世の中になって欲しいものだと考えています。
実務へのヒント
1. 医療的か業務的かを意識する:困っている事例が出たときは、まずそれが医療的な問題なのか、業務的な問題なのかを整理することが重要です。混同は対応を曇らせます。
2. 会社の判断責任を自覚する:業務的健康管理の判断は、会社側が行うべきです。医者に丸投げするのではなく、労働契約に基づいた判断を自らが行う覚悟が必要です。
3. 契約に立ち返る:迷ったときは、常に「労働契約とは何か」に立ち返ることが、現実の混乱を整理する最強のツールになります。