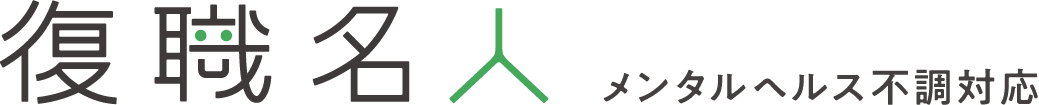今回は、AMA(American Medical Association=米国医師会)が出版している、復職に関する医師向けガイドラインを取り上げます。このガイドラインの第2章に出てくる3つの概念は、私たちがこれまで主治医意見の取り扱いについて議論してきた内容と、非常によく噛み合います。
*本記事は「復職名人が読む三手先」第82回の内容をもとに構成しました。
3つの概念:Risk・Capacity・Tolerance
ガイドラインでは、医師が就業能力や復職について意見を求められた際に、意識すべき3つの概念が整理されています。
Risk
従業員が特定の業務に従事することによって、本人、同僚、あるいは一般市民に何らかの害をなすおそれがあるというものです。
ガイドラインで挙げられている例は、コントロール不良のてんかんの場合にはパイロットやタクシー運転手に従事させないという、米国運輸省の規定です。日本に置き換えれば、糖尿病の血糖コントロール不良で運転制限をかけるとか、血圧が高いので高所作業を制限するといった、定期健康診断の事後措置としてすでに行われている就業上の措置に近い考え方です。
このRiskに対する対処はwork restriction(就業制限)と呼ばれています。ガイドラインでは非常にわかりやすい表現で、”something an employee can do, but should not do”(本人はできるが、やらせるべきではないこと)と説明されています。てんかんであれ血糖コントロール不良であれ、本人はやろうと思えば運転業務をできるが、事故を起こすリスクを考えると、会社としてはやらせるべきではない。そういう整理です。
またRiskについては、科学的・医学的に根拠があることが前提です。根拠があるものについては、医師の間でも意見が一致しやすいとされています。
Capacity
筋力、柔軟性、持久力など、主に身体的な能力を指します。科学的・医学的に測定可能なものです。
例えばテキストに出てくるのは、6METsの負荷を頻繁に要求するような業務なのに、本人に4METsかけた段階で最大心拍に達してしまう場合、6METsの負荷を頻繁に要求するような業務はできませんから、それは復帰させられませんという話です。あるいはもっと単純に、握力が10kgしか出ないのに、業務上20kgが求められるのであれば、そもそもできませんということです。
ただし、テキストを丁寧に読んでいくと、この概念もなかなか難しいことがわかります。
というのも、測定結果は能力だけでなく、本人のやる気にも左右されてしまうからです。100mを25秒で走ったとして、25秒でしか走れないのか、手を抜いて25秒になっているのか、医師には区別がつきません。テキストにもはっきり書いてありますが、医師が測定できるのはあくまでも「現時点での能力(current ability)」に過ぎず、その測定を受けたということは、本人がワークアビリティの評価を受ける意思を示した、ということに留まるのです。
Tolerance
今回ぜひ一番紹介したい概念です。
従業員がある業務を求められる水準で行うことはできるが、痛みや疲労などによって快適にはできない。そのため、本人がその業務を「やるかやらないか」を選択しているというものです。要するに、しんどいからやらない、ということです。
テキストに挙げられている例がわかりやすくて、現在の賃金だとやりたくないが、3倍の賃金をもらえるなら喜んでやりますと。そういう類のものです。
そしてここが最も重要な点ですが、Toleranceについては医師に意見を求めるべきではない、とガイドラインに明記されています。科学的に測定も検証もされないものであるがゆえに、医師の間で意見の不一致が生じるものであるとも書かれています。
日本の復職支援の現場に当てはめると
この3つの概念を知ったうえで、私たちがいつも例に挙げてきた問題を考えてみましょう。
「異動が望ましい」はToleranceの問題
精神疾患の主治医意見の中で、原職復帰に対して「異動が望ましい」とか「軽減勤務が望ましい」と書かれていることがあります。これを3つの概念に当てはめるとどうなるでしょうか。
繰り返し説明してきたことですが、職務を限定しない労働契約において、原職の業務に従事できないということは、「指示された業務は行いたくないが、自分のやりたい業務ならやる」と言っているのと同じです。これはまさに、現在の条件では「やりたくない」が、条件が変わればやるという、Toleranceそのものです。医師が言っているわけではなく、本人が選択している(choose)だけなのです。
「フルタイムはできないが半日程度なら働ける」というのも同様です。半日勤務なら大丈夫で終日勤務だと悪化するという医学的根拠があるなら、それはRiskの議論になり得ますが、そうした根拠がないとなると、本人が終日働くとしんどいから半日しか働きたくないという話と変わらなくなってきます。
精神疾患における条件付き復職は、ほぼ全てTolerance
では、精神疾患においてRiskやCapacityの概念は成り立つのでしょうか。
極論を言えば、精神疾患においてはRiskもCapacityの概念もほぼ成立しません。Riskを裏づける科学的根拠がほとんどないですし、Capacityについても、デスクワークの精神的な側面を客観的に測定する手段がありません。テキストの第22章で精神疾患が取り上げられていますが、主観でしか担保されないものについては議論が成り立たないということがはっきり書かれています。
つまり、精神疾患に関してはほぼ全てがToleranceの問題ということになります。
産業保健の関わり方が、身体疾患中心から精神疾患中心の時代になって、何か「やりにくさ」を感じていたとすれば、その正体はまさにここにあるのではないでしょうか。Toleranceに過ぎないものを、あたかもRiskの話のように、あるいはCapacityの話のように、すり替えてしまっていた。しかも、すり替えている意識すらなかった。そこが問題の本質だったということです。
主治医と産業医の「代理戦争」の原因
主治医と産業医の意見が一致しないという問題は、日本の産業保健で長年の課題とされてきました。
しかしガイドラインの整理を踏まえると、原因はシンプルです。自由記述で意見を求めてしまったために、Risk・Capacity・Toleranceがごちゃ混ぜになった回答が返ってきている。そしてToleranceについて述べられたものを、医学的意見として扱ってしまった。これが主治医と産業医の「代理戦争」につながっていたのではないかということです。
ちなみにこれは日本だけの問題ではなく、米国でも同じだったようです。だからこそ米国では、雇用主側や保険者側が様式(フォーム)を作って、Toleranceが混入しないように聴取する形になっているとのことです。私たちが主治医意見書の様式を開発してきたのと、全く同じ発想です。
前書きでの重要なメッセージ
ガイドラインの前書きにも、非常に重要なメッセージがあります。
医学教育では復職を教えていない
ガイドラインの前書きでは、こんな趣旨の記載があります。「医師は医学教育の中で、復職に関する事項を特別学ぶ機会がない」と。これは日本だけの話ではなく、米国においても同様だということです。
それにもかかわらず、「雇用主も従業員も、診断書に書かれた復職に関する記載が専門知識に基づいていると思い込んでいる。だからこそ、このテキストが作られた」という背景です。
復職の判断は従業員と雇用主が行うもの
復職の判断は常に従業員と雇用主が行うものであり、医師の役割は単なるアドバイザーに過ぎない。
日本の現場では、「ドクターストップ」という言葉に象徴されるように、医師が復職の可否を決めるかのように捉えられがちです。しかしガイドラインの立場は明確で、何をどのように働くかはあくまで従業員と雇用主の二者間の確認事項であり、そのほとんどは医学の問題ではありません。
医師は目一杯言えることは言ってあげてもいい。ただし、医学的根拠のないことは、「目一杯言うこと」に含めてはならない。これがガイドラインの立場です。
実務にどう反映するか
主治医にとっても助けになる
多くの主治医は、復職に関する意見を求められることに対して、実は困っていました。「それは私たちに聞かれても困るんですよね」という声は、臨床の精神科の先生方から意外と多く聞かれるものです。
今までは頼まれたからしょうがなく書いていた。でもToleranceという概念を知れば、「これは医学的に答えられる問題ではない、本人が自分で言うべきことだ」という整理ができるようになります。本当は答えるべきではないということが、医学的な観点としてもそうであったとわかれば、主治医にとっても頭の整理になるはずです。
これまで私たちが労働契約の観点から整理してきたことに対して、感情的に受け入れ難かった主治医もいたと思います。「労働契約でそうなっているんです」と言われて、「それなら契約を変えてあげてくれ」と言いたくなる気持ちは、臨床医としては自然なものでしょう。しかし、AMAガイドラインという医師向けの文書でも同じ結論が示されている。これは一つの説明材料になるのではないでしょうか。
主治医への意見聴取を変える
具体的には、主治医に意見を聴取する際に、あらかじめRisk・Capacity・Toleranceの整理を伝えたうえで、「Toleranceについてはお尋ねしませんし、お答えにならないようにお願いします。仮にお答えいただいても、Toleranceの範疇であると判断するものについては、先生のご意見に左右されません」と先に伝えることが考えられます。
もちろん、すべての主治医に理解してもらえるわけではないでしょう。ただ、「なるほど」と思う先生はかなりいるのではないかと考えています。
Riskはゼロベースで聞く必要はない
Riskについては、これまで蓄積してきた疾患と就業制限の組み合わせがすでにあります。わざわざゼロベースで主治医に聞かなくても、本人の基礎疾患と治療・療養の経緯から、「当社としてこのような就業制限を考えています。これ以外に医学的根拠をもって提案し得るものがあれば言ってください」という聞き方で足ります。
あるいは、定期健康診断の事後措置の中で理論的にはすでに議論されているはずのものです。いつも言っているように、今働いている人に対して就業制限を発動するのは難しいですが、一度休職している人であれば、復職時にあわせて整理することはすっきりできるでしょう。
Capacityは日本の雇用では意味が薄い
Capacityは、特定の職務遂行能力を前提としたジョブ型雇用だからこそ生きてくる概念です。「この業務ができるかどうか」が明確に問われる場合には、筋力や持久力の測定に一定の意味があります。
しかし、職務を限定しない日本の雇用においては事情が異なります。日本の復職判断で問われているのは、「客観的にその業務をこなせるか」ではなく、「言われたらやるつもりがあるか」という心意気の問題であることがほとんどです。「やるつもりがある」と言っておけばいい話であり、それを医師が「できます」と担保することにも、科学的根拠はありません。
つまり、Capacityの問題に見えるものの多くは、日本の雇用に当てはめると実質的にはToleranceの問題ということになります。
自社のルールとして落とし込む
AMAガイドラインは米国の文書であり、日本の雇用に直接適用されるものではありません。また、ジョブ型雇用を前提とした議論なので、日本のメンバーシップ型雇用にそのまま当てはめられない部分も当然あります。
重要なのは、この概念を右から左にそのまま使うのではなく、「当社として、AMAガイドラインに示される考え方を検討し、労使で協議した結果として採用した」という形で、自社のルールに落とし込むことです。そうすれば、仮に主治医からAMAガイドラインについて何か言われようとも、「当社でそうしているんです」という話にできます。
そのように労使間の約束として運用すれば、司法の場においても、何の根拠もなく採用した基準ではないということで、合理性を認められることにもつながってくるのではないでしょうか。
Toleranceという概念を知ることで、今まで漠然と感じていた「ボタンの掛け違い」のようなものに、一つの整理がつけられるのではないかと考えています。診断書に書かれた主治医意見に対して、それはRiskなのか、Capacityなのか、Toleranceなのかを仕分ける。多くの場合、それはToleranceであり、本来は医師ではなく本人が自分で言うべきことです。
これまでも二つの健康管理の整理を毎回お伝えしてきましたが、このRisk・Capacity・Toleranceの整理は、今後どの場面でも繰り返し紹介していきたいと考えています。