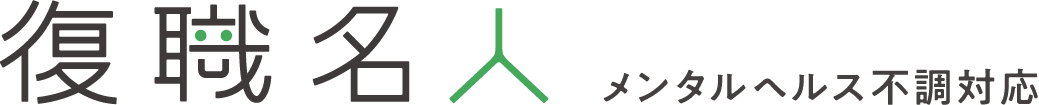休職からの復職において、「人間関係が原因だから異動させた方がよい」「本人のためを思って配置転換を検討する」といった対応は、一見すると配慮のように見えます。しかし、この「善意の配慮」が、実は多くの問題を引き起こす可能性があることをご存知でしょうか。
本記事では、休職からの復職における「原職復帰の原則」の重要性と、安易な異動判断がもたらすリスクについて解説します。
*本記事は「復職名人が読む三手先」第54回の内容をもとに構成しました。
よくある相談事例
人間関係のストレスで休職した社員が復職する際、元職場への復帰が基本だと思いますが、職場の方から「原因となった人と引き離すために班を変えたり、本人の経験や資格を生かせる部署に異動させたい」という要望があります。
どちらが明らかに悪いということではなく、馬が合わないことでお互いストレスとなり生産性が下がる懸念がある場合など、引き離した方が職場としても管理しやすいように思います。
会社の都合、総合的判断での異動と考えれば、問題ないでしょうか。
人事の現場では、ごく自然な判断に思えるかもしれません。
しかし、このよかれと思った「配慮」が、組織に新たなリスクを生む可能性があります。本記事では、復職支援における原職復帰の原則を軸に、異動による引き離しに潜むリスク、そして労災が絡むケースでの考え方を整理します。
1. 「馬が合わない」は原職復帰の例外にならない
原則のおさらい
復職時の基本は「元の職場・元の職務・元の職位」への復帰です。この原則の例外が認められるのは、元の職場・職務・職位のいずれかが業務上の都合により消滅した場合に限られます。
ここで重要なのは、「人間関係の不和」や「馬が合わない」という事情は、この例外要件に該当しないという点です。

なぜ異動させてはいけないのか──3つのリスク
① 本人が納得するとは限らない
会社としては「配慮」のつもりでも、本人は「なぜ自分が動かされるのか」と受け取る可能性があります。「悪いのは相手の方だ。相手を異動させるべきだ」という主張に発展し、主治医を巻き込んだ対立構造(いわゆる「主治医対産業医の代理戦争」)に陥るリスクがあります。さらに、異動先が気に入らないとして「異動先への配属がストレスになる」という診断書が提出される可能性も否定できません。
② 横・縦の公平性が崩れる
Aさんに異動配慮を行えば、Bさん・Cさんからも「自分も馬が合わない上司がいる。異動させてほしい」という要望が出てきます。さらに、「休職すれば異動してもらえる」という誤ったメッセージを組織全体に発信してしまう恐れがあります。
また、一度「引き離し」で対応すると、同じ社員が再び人間関係の問題を抱えた際に「前回も異動させてくれたじゃないですか」と前例化します。会社が配慮すればするほど、本人の自律的な対処能力の発達が妨げられ、問題が繰り返される構造ができてしまいます。
③ 恣意的な人事の問題
「総合的判断」という名のもとで、ケースごとに異なる判断をすることは、結果として恣意的な人事につながります。「この人には配慮するが、この人にはしない」「このケースでは異動を認める、別のケースでは認めない」というのは、どのように合理的な説明ができるでしょうか。
このような、純粋に業務上の都合のみを持って行なわれたとは言えない、不当な動機を持ってなされた異動は、単に公平性を欠くというだけでなく、訴訟リスクを高める可能性があります。
2. まず本人に「原則」を伝えることから始める
復職支援の現場で見落とされがちなのは、本人に原職復帰の原則をきちんと説明するプロセスそのものです。
多くの場合、「引き離した方がいいか?」という検討は、産業医や人事の間だけで行われ、本人には事後的に結果だけが伝えられます。しかし本来は、まず本人に「復職先は元の職場です」と伝えること。これが出発点です。
原職復帰の”原則”の注意点
皆さんに説明をする際には、原職復帰の原則と呼んでいますが、本人に説明をする際に「原職復帰が原則です」と言うと、「じゃあ、私の場合は例外として異動を認めてください」と言われることに気づきました。
そのため最近は「復帰の際には、原職復帰です」とだけ伝えるようにしています。
復職時と復職後を分けて考える
ここで実務上特に重要なのは、病気と配属先を結びつけないという考え方です。
復職の時点で異動をセットにするのではなく、まず原職に復帰させる。そのうえで、復職後に通常の業務遂行状態に移行した段階で、生産性や業務適性の観点から異動を検討するのであれば、それは通常の人事判断として対応できます。
つまり「復職時にやるからおかしくなる」のであって、復職後の通常管理の中で判断すれば、特段問題のない話になるケースが多いのです。
3. 「原因の決めつけ」にも注意を
質問の前提にある「人間関係のストレスで休職した」「原因となった人」という表現にも、注意が必要です。
メンタルヘルス不調の原因は多要因であり、本人や主治医の申告だけで「この人が原因だ」と断定することには慎重であるべきです。主治医意見書に「職場の人間関係が原因」と記載されていたとしても、それが本人の申告をそのまま記載したものである可能性もあります。
原因の特定と対策を短絡的に結びつけること(「原因がAさんだから、Aさんと離す」)は、恣意的な人事判断につながりかねません。
4. 労災認定は原職復帰の例外になるか?
もう一つの論点として、
- 月100時間超の時間外労働による心脳血管疾患で後遺症が残った場合
- 業務中の交通事故で後遺障害が残った場合
など、「会社側に責めに帰すべき事由がある場合は、例外になるのでは?」という質問もあります。
結論:労災認定の有無は、原職復帰の原則に影響しない
労災認定されるかどうかという問題と、原職復帰であるかどうかは別の問題です。労災だからといって原職復帰の原則の例外にはなりません。
対話を怠ると「会社のせい」に転化する
注意すべきは、労災に該当する(またはその疑いがある)ケースで、会社が後手に回った場合の展開です。「業務のせいで病気になった」→「業務のせいなんだから会社のせいだ」→「会社のせいなんだからこれくらいの配慮は当然だ」──この転換が、対話を避けているうちに本人・家族の中で進行します。
この心理の変化に気づかず放置すると、後から大幅な譲歩を迫られることになります。最初から丁寧に対話し、方針を明確に示しておくことが、結果的に双方にとって最善の対応となります。
よくある混同:「会社のせいなのだから雇用条件を維持すべき」
労災事案で頻繁に見られるのが、「会社のせいで病気になったのだから、従来の条件で雇用を維持すべきだ」という主張です。しかし、法的に整理すると、これは2つの異なる問題を混同しています。
労働者としての地位(雇用関係の維持)と、安全配慮義務違反に対する損害賠償請求権は、本来別々の問題です。就労能力が低下した分の損害は、損害賠償という制度で補填されるべきものであり、「雇用条件を下げないこと」でバーター的に解決する話ではありません。
会社から労働条件の変更を切り出すことのリスク
もう一つ実務上注意すべき点があります。就労能力が低下した社員に対して、会社側から「勤務時間を短縮しましょう」「賃金を下げて雇用を続けましょう」と提案することは、一見すると解雇回避の努力に見えます。
しかし番組での議論では、会社側からの労働条件の切り下げ提案は、実質的に契約の一方的解消(=解雇)の申し入れと同義であり、解雇回避努力には当たらないという見解が示されました。本人が自ら「現在の契約条件では業務遂行が難しい」と認識し、条件変更を申し出る場合とは、法的な意味合いが大きく異なります。
5. 「メソッド」とは何か
メソッドの本質
高尾メソッドとは、事前に労使で話し合い、ルールを決め、計画的に実行するという方法論です。
これに対し、「メソッド以外」のアプローチとは、本人や主治医が言ってきてから、その都度対応を考えるという後手後手の対応であると言えるでしょう。
なぜメソッドが必要なのか
後手後手の対応を続けると、以下のような問題が生じます。
- 感情的な対立が深まる
- 「会社は従業員を辞めさせようとしている」という誤解を生む
- 一生懸命支援した結果、裏切られたと感じ、関係が悪化する
- 恣意的な判断により、公平性が失われる
メソッドの目的は、辞めさせることではなく、そもそも「辞めさせたい」と思う状況を作らないことです。
6. 実務上の注意点
重要原則
- 原職復帰が原則:元の職場、元の職務、元の職位への復帰
- 例外は限定的:業務上の都合による消滅のみ
- 配慮は例外に該当しない:人間関係への配慮は業務上の都合ではない
避けるべき対応
- 本人に伝えずに異動を検討する
- 復職とセットで異動を提案する
- ケースごとに異なる判断をする(恣意性)
- 病気と人事異動を結びつける
推奨される対応
- 原則を明確に本人に伝える
- 本人からの異動希望は通常の人事異動として扱う
- 復職後の異動は業務評価に基づいて判断する
- 就業規則に原則と例外を明記する
まとめ:「配慮」の落とし穴
真の配慮とは、明確なルールに基づき、公平に対応することです。
復職対応で最も重要なのは、事前にルールを定め、計画的に・一貫して運用することです。「従業員のために」「本人のことを思って」という善意の配慮は、短期的には「無難に収まった」ように見えても、組織全体の公平性と信頼を中長期的に損ないます。
感情や善意に流されず、論理的で一貫性のある対応を心がけることが、結果として従業員にとっても、会社にとっても、最善の結果をもたらします。
判断に迷ったときは、「他の社員が同じ状況になったとき、同じ対応ができるか?」と自問してみてください。その問いに自信を持って「はい」と答えられる対応こそが、全員にとって公正な職場環境をつくる土台になります。