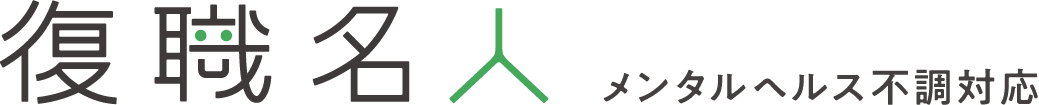復帰時は、元の職場・元の職位・元の職務への復帰を原則とする。これを原職復帰の原則と呼んでいます。
この原則の唯一の例外は、原職がなくなった時です。
例外ばかりの従来型対応
実は、復帰時は原職への復帰とする、というルールは、多くの企業・自治体でも定められています。ところが問題は、多数の例外があることです。
代表的な例は、主治医の先生の意見。つまり「異動が望ましい」という意見が出た場合には、復帰を検討するという例外です。同様に、本人に確認してみたところ、「元の職務では負担が大きいので、業務を調整して欲しい」という希望も例外として取り扱われます。
あるいは、職場上司の意見。あの従業員は戦力にならないから、異動させてくれ、というかなり乱暴な意見です。人事がこれに同調していることもあります。
これらの例外をすべて考慮していると、「原則」はどこにあるのか、全く分からない対応になってしまいます。この点が、従来型対応の問題点です。
原職復帰の例外は、原職がなくなった時のみ
一方で、復職名人における考え方は極めてシンプルです。例外は原職がなくなった時のみとしており、それ以外は原職復帰としています。特に長期療養者の場合、原職がなくなることが稀にあります。
例えば、元の職場が無くなってしまった時。部署の統廃合などで職場が無くなってしまったら、原職復帰はできません。
また、元の職務をアウトソーシングしてしまった時。元の職務をさせようにも、その職務自体がないのですから、原職復帰はできません。
そして、元の職位を空位にできず、別の人を充てていた時。特に職位が高い従業員が休職に入った場合に、いつまでも●●代理の人に業務を命じることができず、交替することがあります。この場合もまた、原職復帰はできません。
そして重要な点は、これらはすべて、会社の事業上の都合によって生じたものである、ということです。決して、病気への配慮として行うものであってはいけません。ましてや、長期療養者に対する報復として行ってもいけません。
原職以外に復帰する際の注意点
復帰基準は原職も遂行できること
仮に復帰時に原職復帰の例外となったとしても、復帰基準における業務基準は変わりません。元の職場で元の職務を職位相当従事できることです。要するに、実際に配属するかどうかと、業務遂行ができるかどうかは別問題だということです。
この確認をすることで、復帰後すぐに配属することはできなくても、今後の人事異動で配属される可能性は、他の人と同じように残っている、という状態で復職させることができます(逆にこの確認をしなければ、今後の人事異動で、療養開始時点の部署は配属できない職員を生み出してしまうことになります)。
復帰後の業務パフォーマンスの見極めは丁寧に行う
復帰後、業務遂行が職位相当最低8割できているかを確認することになりますが、原職以外への復帰をさせていると、この見極めが難しくなります。つまり、原疾患の再増悪によって職位相当の業務ができていないのか、新たに従事し始めた慣れない業務だから、パフォーマンスが発揮されていないのか分かりません。
そのため、この点をしっかりと整理した上で、パフォーマンスの評価をする必要があり、評価する側にとっては少し難しい対応を迫られることになります。なお、どちらかと言えば、安全側にマージンを取る意味で、原疾患の再増悪に起因することを否定できないパフォーマンス不足として、取り扱っておくと良いでしょう。
あらかじめ説明しておく
原職以外の復帰は、慣れない人間関係の元で慣れない仕事に従事することになります。これは、従業員側にとっても原職に復帰するよりも難しい復帰となります。
そのため、重要な点は、原職復帰の原則を適用できないことが想定された時点で、あらかじめ原職以外の復帰となることを説明しておくということです。面接シナリオを準備して、丁寧に説明しておきましょう。