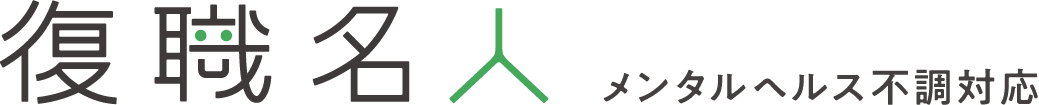今回は、休職に関連して最も重要な規程と言って良い、通算規程について説明します。
私たちが支援する会社においても、通算規程の整備ができていない場合は、真っ先に取り組むようアドバイスしています。というのもこの規程がないと、何度でも繰り返し休職を取得できることになってしまい、終わりが見えなくなる(あるいは、強硬手段に出ざるを得なくなる)からです。
しかしながら、規程を整備している会社であっても、その規程の仕方に穴があり、結局繰り返し事例に苦労しているケースも少なくありません。
一般的な通算規程の問題点
通算規程とは、復職後、再度私傷病欠勤や休職をした場合に、復職前後の欠勤や休職期間を通算する制度のことです。
よくある規程例
今では、多くの会社で通算規程が整備されていると思いますが、次のような規程をしている会社が多いのではないでしょうか。
復職後半年以内に、同一または類似の傷病により、再度欠勤を開始した場合は、その前後の欠勤及び休職期間を通算する
同一または類似の傷病を誰がどのように判断するか
この規程の問題点は、通算の条件を「同一または類似の傷病」としている点です。
同一または類似の傷病であることを、誰がどのように判断するのでしょうか。
メンタル疾患で休職した社員が、違うメンタル疾患名で再度休み始めることや、腰痛や頭痛などの身体症状を理由に休み始めることはまれではありません。その場合に通算規程を適用できるでしょうか。あるいは、違う病名の診断書が、本人から提出された場合には、どうでしょうか。
このように、傷病そのものにとらわれていると、通算規程を適用できるかできないかに関して、医師の意見に左右され、会社としての明確な対応は難しくなります。また医師は、裁量の範囲で本人の不利益を回避できるような意見を述べる傾向があることは、医師患者関係という医療契約を考えれば当然のこととも言えます。
何とか半年乗り切ってしまうケースも出てくる
また、ほとんど通常勤務できているとは言えない、勤務状況で何とか半年乗り切って、すぐに再休職するケースもあります。
こうした事例を経験・想定している企業の中には、通算できる期間を延ばそうとしているところもあります。ただ、あまりに長い通算期間への変更は、合理的とは言えないため、長くても1年程度が限界という印象です。
通算規程の中に勤怠要件を含める
問題の本質は、会社と労働者の二者間で判断できない点
そもそも上記のような一般的な通算規程に潜む問題は、会社と労働者の雇用契約上の労働条件を定めるべき就業規則において、二者間のみで判断できないような定め方をしてしまっている点にあるといえます。
そのため、医師の意見に影響されない、つまり病名に依存するのではなく、二者間で判断できる基準を「通算規程として」定めることで、問題を解決できるでしょう。
規程例
では、どのようにすればよいかというと、「勤怠の要件」を定めることをおすすめしています。
これまでも説明してきましたが、例えば再療養に入るための、ストップ要件も、メインは勤怠の要件で構成されています。
これは、勤怠は白黒はっきりつくため、要件への該当が、客観的に明確になるからです。仮にこれを「通常勤務ができているとは言えないとき」と定めてしまうと、本人は通常勤務できていると主張し、職場はできていないと主張する、泥沼状態が発生することを容易に想像できます。
通算要件も同じように、勤怠を用います。
休職から復帰後、連続した6ヶ月において無遅刻・無早退・無欠勤を遵守でき、かつ事前に適切に申請することなく業務に従事できないこと(事後的に有給休暇取得を認めた場合も含む)などがなかった場合には、それ以前の休職期間は、次の休職期間に通算しない。ただし、療養の原因となった傷病に関連しないことが明らかである特別な事情があると、会社が認める場合は除く。
規程例の解説
この規程例は複雑で少しわかりにくいので、補足説明をします。
まず通算規程は、6カ月間、遅刻早退欠勤などの勤怠の乱れがないことによって、通算“されない”規程になっております。
もし復職直後の6カ月間に勤怠の乱れがなければ、それで通算は終了となります。だらだらと数カ月に一回遅刻を繰り返し続ければ、6カ月勤怠の乱れがない期間ができるまで、ずっと通算されることになります。
ただし、明らかに特別な事情であることを、会社が認めた場合には、勤怠の乱れには含めないことにしています。
ここで想定される例外は、悪天候による交通機関の乱れや、インフルエンザなど明らかに原疾患とは関係ない休みです。これらは会社が認めた場合としていますので、場合によっては証明書等を提出してもらうこともあります。
また、メンタル休職後の頭痛や腰痛などは、明らかに関連しないとまでは言えませんので、特別な事情とは認められません。
なお、有給休暇などの休暇等についても、適切な事前申請等がなければ、勤怠の乱れとしてカウントします。
有給休暇の取得そのものではなく、適切な申請ができていないことに注目しています。
また、この点についてよく誤解があるのですが、当日申請の有給休暇について、会社として取得を必ずしも認めなくてはならないわけではありません。
簡単に説明すると、有給休暇は本人による時季指定権と、会社の時季変更権で構成されています。時季変更権の行使は、よほどのことがなければ難しいですが、一方で、その考慮さえもできない、当日の休暇申請は問題と言えます。そのため、多くの規程では有給休暇は事前申請制としており、それに準じた対応を求めるわけです。
繰り返しになりますが、このように会社が適用可否を判断できる無いようにしておかなければ、規程の網をすり抜けてしまう例があることは常に認識しておかなければなりません。